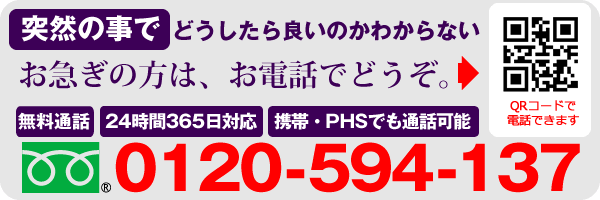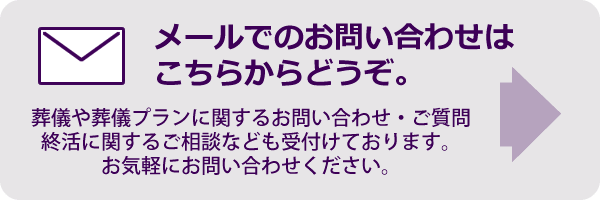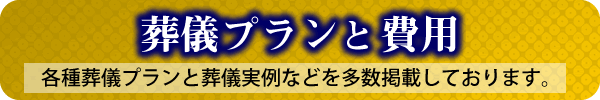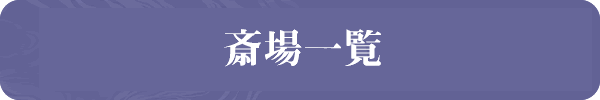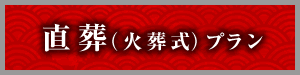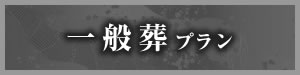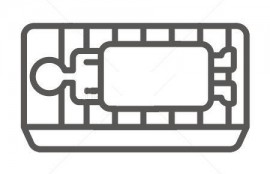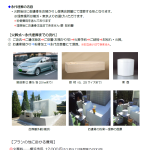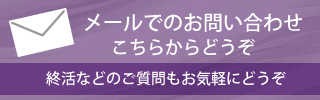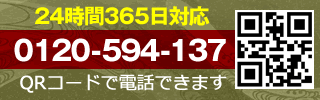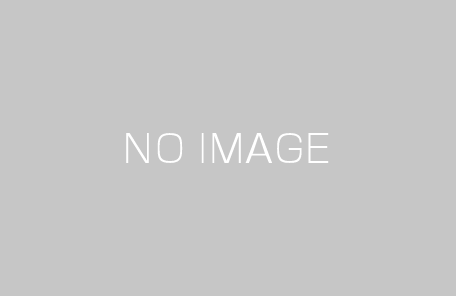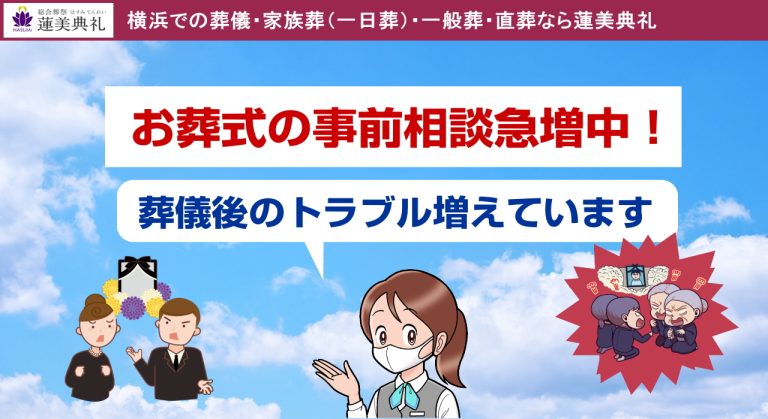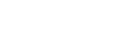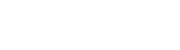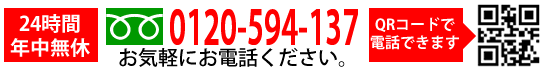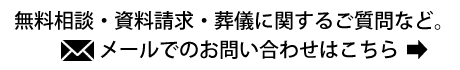**祥月命日(しょうつきめいにち)**とは、故人が亡くなった月日と同じ日を指し、亡くなった翌年以降、毎年行う供養のことをいいます。
「忌日(きじつ)」とも呼ばれることがあり、家族や近しい人が故人を偲んで供養を行うのが一般的です。
祥月命日の意味と由来
祥月命日の「祥(しょう)」は、もともと儒教の言葉で「さいわい(幸い)」を意味します。
これは、「故人の死を悼む中で、悲しみを越えて吉へと向かうことを願う心」が込められている言葉です。
そのため、祥月命日はただ悲しむだけの儀式ではなく、前向きな供養でもあります。
祥月命日に供養を行う人は?
祥月命日の供養は基本的に遺族だけで行うのが一般的です。
ただし、故人と親しかった方やお世話になった方が招かれることもあります。招待を受けた場合は、可能な限り出席するのがマナーです。もし参加できない場合は、お供え物とともにお詫びの気持ちを伝えるようにしましょう。
祥月命日の供養方法とお供え物
供養は仏壇の前で行うこともあれば、墓前で行うケースもあります。方法は地域や家庭によってさまざまですが、代表的なものは以下の通りです。
● 仏壇での供養
-
お線香をあげる
-
供花(きょうか)を供える
-
故人が好んでいた食べ物や嗜好品をお供えする
● 墓前での供養
-
お坊さん(住職)にお経をあげてもらう
-
卒塔婆(そとば)を立てて供養する
卒塔婆供養では、古い卒塔婆がたまってきたタイミングで、お経をあげて焼却供養を行うこともあります。
お布施の渡し方とタイミング
お坊さんにお経をお願いする場合は、「お布施」が必要です。金額は地域やお寺によって異なりますが、供養が始まる前に直接手渡しするのが一般的なマナーです。
よくある質問(FAQ)
Q. 祥月命日はいつから始めるの?
A. 故人が亡くなってから1年後、つまり一周忌の翌年から毎年同じ月日に行います。
Q. 参加できない場合、どうすればいい?
A. お供え物(供花やお菓子など)を贈り、欠席のお詫びを伝えるのが望ましいです。